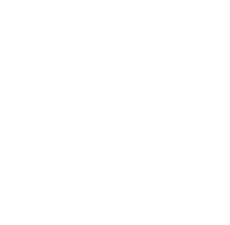はじめに
久しぶりに技術ではないプライベート記事です。
とはいえ、間接的に仕事に関係していますが。
これまで、ある程度のリモートワーク環境を整えてきました。
例えば、以下のようなものを購入しました。
| 項目 | 購入物 |
|---|---|
| モニター | LGの安物モニター x3 |
| マウス | LogicoolのMX Master 3 |
| キーボード | LogicoolのMX Keys mini |
| 電動昇降デスク | FLEXISPOTのE7 |
| 椅子 | イトーキ サリダチェア |
コスパを求めてあまりこだわりが無い環境だったんですが、WEBエンジニアかつリモートワーク中心の生活が3年を迎えるので、少し環境を整えてみようと思います。
動機
エンジニアとしての不安
ある程度お金をかけてでも環境を整えようと思ったのは、エンジニアとしての不安が大きいからです。
ソフトウェアに関わるようになって5年がすぎ、WEB業界にきて3年が経ちます。
もうこんなに経験を積んでいるのに実力はこんなもんか、と感じることが多くなってきました。
技術書の内容やネットの情報を読むことはできても、それを体験するにはあまりに時間も経験もなく、人生に対してあまりにコンピュータの世界は広すぎると感じていました。
私はあまり要領が良くないので、経験に対して実力をつけるために効率を上げることより、そもそも1日の中で技術に触れる時間を伸ばす、というのがこの1年間のテーマでした。
身体面の限界
ただ、これには限界がありました。 1日12時間を超えてくると翌日の肩こり、首こりがひどく、かえって効率が落ちることが多かったです。
人類には8時間以上のデスクワークは無理なのかもしれない。
個人的な理想はもう脳みそを直接PCに繋いで労働したいんですよね。脳より先に身体が疲れてしまうので。
27歳の今でこれなので今後の人生を考えると早めに投資したほうが日割り安くなるなと思いました。
そもそも趣味のゲームをしている時間も座っているので、椅子にお金を書けても十分にもとが取れそうです。
購入物
- アーロンチェアリマスタード
- HatsuKey70(分割キーボード)
基本的に悩んでいるのが肩こり、首こりなので、椅子とキーボードを変えてみることにしました。
アーロンチェアリマスタード
こちらは説明の必要がない有名な椅子です。
大阪にはハーマンミラーのショールームがあるので、試座して購入しました。
今まで利用していた椅子と比較すると、肘置きの間隔が狭く、正しい姿勢以外できないような作りになっていますが、キーボード操作時も常に肘置きに腕が乗っている状態を保つ事ができます。
また、高さや肘置きの前後、角度を調整できる点も良いです。
何より、腰部分のサポートによって常に背もたれを利用する形になることでお尻への負担が減り、長時間座っていても疲れにくいです。
なにげにメッシュの椅子も初めて利用したのですが、通気性の良さも非常に快適です。
座っているときは多少の窮屈さを感じるんですが、1日終わったあとの疲労がかなり軽減されている感じがします。
HatsuKey70
こちらは分割キーボードです。
アーロンチェア同様、肩こり、首こり対策として購入しました。
キーボードにこだわりが一切ない人生を送ってきたんですが、肩こりを考えると分割したいなと思うようになりました。
キーボード自体にこだわりはないので割れていてMacBookと同様にロープロファイルのものを探していたんですが、既製品だと選択肢がかなり少なく、自作することにしました。
高専の授業以来のハンダ付けでしたが、無事に組み立てることができました。
その他取り組んでいること
いくら環境を整えたとしても、やはり完全に肩こりを解消することはできなかったんですが、下記の取り組みをしていると少し改善されている気がします。
ジム通い
1年くらい前に稼働を上げたいと考え始めたときに始めたのがジム通いでした。
現在も継続して通っていますが、肩こりがひどすぎるときに運動すると急に血流が流れて気持ち悪くなることもしばしばありました。
多分そんなに凝ってるほうがおかしいんですが。
ストレッチポールの利用
陸上部だったときからずっと利用しているのがストレッチポールです。
割と人生で購入して良かったものの上位に入ります。
これを使って肩甲骨周りをほぐすと、肩こりがかなり軽減されるので、毎日の習慣として続けています。
特に寝る前と寝起きに少しストレッチするだけで、翌日の肩こりがかなり軽減されるのでおすすめです。
まとめ
もう少し早く椅子には投資してもよかったなと思います。
椅子と同時にキーボードを頼んだんですが、椅子でかなり改善されるのでキーボードは過剰だったかもしれません。
かなりの出費でしたが、これで少しでもエンジニアとしての成長が加速できればいいなと思っています。